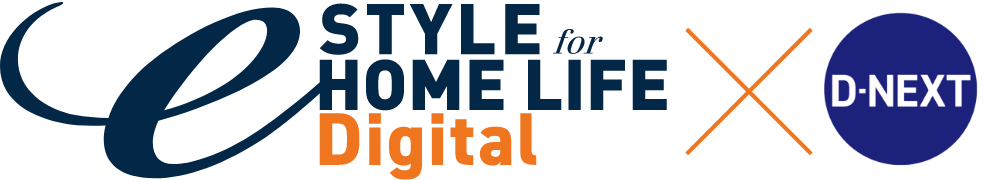安定供給と脱炭素をどう両立するか
LPガスが担う役割と求められるエネルギー改革

2025年3月14日
LPガスの安定調達と供給体制確保は重要
政府はこのほど、中長期的・総合的なエネルギー政策の指針となる「第7次エネルギー基本計画」を閣議決定しました。東日本大震災の経験・反省・教訓が引き続きエネルギー政策の原点としながらも、第6次エネ基以降の国内外の情勢変化も十分踏まえる必要があるとし、S+3E(安全性・安定供給・経済効率性・環境適合)の原則は維持した上で、安全性を大前提に、エネルギー安定供給、経済効率性の向上と脱炭素への適合を図るとしています。
LPガスについては、5章5節「化石燃料/供給体制」の基本的考え方のなかで、「災害の多い我が国では、エネルギーの強靱性の観点から、可搬かつ貯蔵可能な石油製品やLPガスの安定調達と供給体制確保は重要である」と初めて言及されています。

また、災害時には、病院等の電源や避難所等の生活環境向上にも資する「最後の砦」としても、重要なエネルギー源であるとし、「災害時に備え、自家発電設備等を備えた中核充填所の新設・設備強化を進めるとともに、病院・福祉施設や小中学校体育館等の避難所等における備蓄強化、発電機やGHP等の併設による生活環境向上を促進する」としています。
CN(カーボンニュートラル)に向けては、グリーンLPガスの大量生産技術の確立が重要と位置付け、2030年代の社会実装を目指すとしました。その際、内外のプレイヤーの連携の下、海外市場も視野に入れた生産・流通網を含むビジネスモデルの構築や、LPガスのCN対応を推進すべく、カーボンクレジットの利用拡大や、rDME(バイオ由来のジメチルエーテル)を混入した低炭素LPガスの導入に向けた取組等を後押しすると明記しています。
高効率給湯器の導入支援で省エネ後押し
2023年5月のG7広島首脳会合で、「第一の燃料(first fuel)」として位置づけられた省エネルギー。クリーンエネルギー移行に不可欠な要素とされ、第7次エネ基では、「需要側の省エネルギー・非化石転換」の項目で、業務・家庭分野において、「ヒートポンプ給湯機やハイブリッド給湯機、家庭用燃料電池といった高効率給湯器の導入や、設置スペース等の都合から高効率給湯器の導入が難しい賃貸集合住宅向けには、潜熱回収型給湯器の導入を支援する」と政策的に後押しすることが示されています。

経済産業省では、2030年度におけるエネルギー需給の見通しの達成に寄与することを目的に、高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金(給湯省エネ2025事業、令和6年度補正予算580億円)と、賃貸集合給湯省エネ2025事業(同50億円)を用意し、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、高効率給湯器の導入支援を行っています。
日本のエネルギー政策は、経済産業省が策定する「エネルギー基本計画」に基づき方向性が定められています。中長期的なエネルギー供給のあり方や環境対策の指針を示すもので、エネルギー安全保障やCNの実現に向けた重要な政策指針となります。そのなかで、LPガスについては、これまで以上に重要なエネルギー源として位置づけられ、その期待が示されたといえるでしょう。
4万件のパブリックコメントが映し出す課題
なお、今回の「第七次エネルギー基本計画」に対して、パブリックコメントの募集期間(令和6年12月27日~令和7年1月26日)中に約4万件を超える意見が寄せられました。
S+3Eの原則については、全体のバランスをめぐる問題意識が広く共有されていることが読み取れます。経済成長やエネルギーの安定供給を改めて重視すべきだという声がある一方、気候変動への緊急性を踏まえ、再生可能エネルギーや脱炭素技術の導入を最優先で進めるべきだとする意見もあり、経済合理性と環境適合性の両立をどこまで具体的に示せるのかが今後の論点となりそうです。

一方で、CNの実現や新技術の活用をめぐっては、グリーンLPガスや水素・アンモニア燃料、CCUS(炭素回収・貯留)など、技術革新による早期の実用化を期待する声と、経済性や技術的成熟度の面で過度に楽観視すべきではないとする慎重論が並存しています。こうした新エネルギー技術のコスト試算や実用化の時期を正確に見極める必要性が指摘され、政策推進に当たっては両者の意見を踏まえた冷静な検討が求められるでしょう。
また、供給面の改革だけでなく、需要そのものを抑制し省エネや節電を促す施策を強化すべきだという主張も少なくありません。特に住宅・建築物の断熱化や高効率機器の導入を促す支援策を拡充してほしいという意見が多く見られ、実効性ある政策設計やインセンティブの設定によって、国民のライフスタイルや企業活動全体の行動変容を後押しする必要性も示されています。